住所 高知県須崎市西町1−2−1 電話 0889−42−0800
」R土語穎須崎駅より車で5分) 土佐新荘脈より徒歩5分
大 師 堂
年中行事
一月一日=修正会 二月三日=厄除節分会 三月=春彼岸会 四月八日=仏生会
六月十五日=宗祖降誕会 七月二十四日=水子地蔵供養 七月八日・旧七月=孟蘭盆会
八月十九日=大師祭 十月二十四日=地蔵まつり 十一月二十二日=土砂加持法要
十二月二十一日 一ツ石大師会
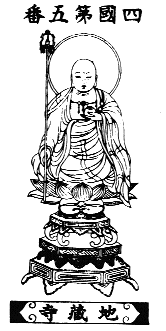 |
 |

四国霊場開祖1200年記念 朱印
大善寺
弘法大師四国八十八ケ所霊場御開創の糊、穎崎の入海はきわめて広く、今の大師堂の地点は海に突き
出た岬となっていた当時は山越しに行くのを常としたが干潮のときはこの二ツ石岬の端を廻って行くことが
できた。ところが同地は波浪いつも岩をかみ王佐の親しらず」といわれ、波にさらわれて海の藻屑となるもの
も多く海難が多発し、そのうえ同地点は伊予石鎚山の末端に当るので身に不浄ある者は時々怪異に出会う
といって恐れられていた。大師は、そのことを聞いて海岸に立つ二つの大岩ので海難横死者の菩堤のため、
海上・陸上の往来安全を祈願して祈祷を行い、一寺を建立したのが今の大師堂の起源である。それ以後は
難儀も軽減したので、誰言うともなく「二つ石のお大師さん」と呼ばれるようになったという。二つの大岩は長年
波荒く打ち寄せる波の力で磯になり丘になり、遂に昭和の初め防潮堤が出来、今はその姿を留めていない
寺伝によれば宝永四年〈丁七〇七竺の大変までは古市町にあり八幡山明星院大善寺といい、法印職の任する
中本寺格として八幡神社の別当職として末寺十七ケ寺を擁していたが寺地境内は六反十二畝三歩・寺は三間
に二十四間だったという記録がある)、津波で流失し古城山のふもとに移ったものらしい。後に明治の廃仏毀釈
により廃寺となり、明治二十九年(一八九六至大師の霊跡を惜しむ里人の手で再興され現在地に移転し寺の
再建を計って今日に至っている。尚、本堂前境内よりのながめは太平洋を眼下に一望でき「二つ石の上でお大師
様」が今もみなさま方の幸せをとこしえに御祈願されております。




四国別格20霊場 四国八十八ケ寺 四国36不動 曼荼羅霊場 お先達します
四国別格20霊場会公認先達
770−8071
徳島市八万町中津山4−129
個人 中村タクシ−
携帯 090−8281−4679
電話 088−653−0280
FAX 088−653−0480