住所 香川県大川郡志度 電話 087−894−0028
| 本尊 十一面観世音菩薩 開基 藤村不比等 本尊の真言 おん まか きやろにきや そわか |
 |
本 堂
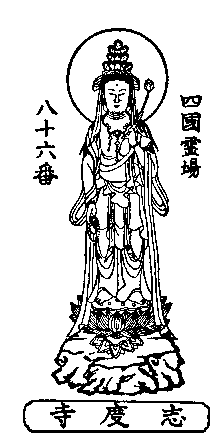 |
仁王門 古く堂々とした構えで、左右の堂門前には大草履が奉納されている。木造金剛力士像は、阿・吟とも鎌倉時代の仏師運慶作と伝えられ、県指定文化財である。 本堂 仁王門とともに讃岐藩主・松平頼重が寛文10年T671)に寄進したもので、本尊とともに重要文化財に指定されている。本尊および両脇侍の不動明王・毘沙門天は、平安初期から中期にかけての作で檜の一木造り。 大師堂 閻魔堂、奪衣婆堂(だつえばどう)などとともに、讃岐国主・生駒正俊が建立したもの。生駒公は房前を祖とする藤原北家の末裔である。堂の背後にそびえる大楠は、弘法大師お手植えと言われている。 |
| 仁王門を入ると左に海女の墓がある。謡曲「海士」で知られる伝説によれば、天智天皇のころ、藤原不比等が亡父鎌足の供養に奈良興福寺の建立を発願した。唐の高宗皇帝の妃であった妹はその菩提にと三つの宝珠を船で送つたが、志度の浦で龍神に奪われた。兄の不比等はあきらめきれず、姿をかえて志度の浦へ渡り、土地の海女と夫婦になり一子・房前をもうける。やがて海女は観世音に祈願し、夫とわが子のために命を捨てて龍神から宝珠をとりかえす。不比等は海辺の近くに海女の墓と小堂をたて死度道場と名づけた。後に房前は母の追善供養に堂宇を増築し、寺の名を志度寺と改めるのである。寺伝によれば推古天皇の三十三年に志度の浦に楠の霊木が漂着し、園子尼がこの霊木で観世音の尊像を刻みたいと念じたのがそのはじまりという。現在の本堂・仁王門は寛文十年(一六七〇)の建立。五重塔は昭和五十年、大阪に出て成功した当地出身の竹部二郎氏の建立推古天皇の御代園の子尼は漂着しに霊木で十一面観音像を刻まんと腐心していると、仏帥姿の男が現れ単日に等身大の像を彫りあげ、「われは補陀落の観音なり」と告げて去った、堂宇建立の際も閻魔王の出現があったという不思議な縁起を秘めた寺であり、事を奉聞された推古天皇は当寺を勅願所に定めたという。 |

お申し込みは下まで
四国八十八ケ所霊場会公認 大先達 お遍路専門タクシー
770-8071
徳島市八万町中津山4−129
徳島個人 中村タクシ− 中 村 功
電話 088−653−0280
FAX 088−653−0480
携帯 090−8281−4679